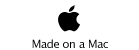私の出身高校(諏訪清陵高校)の偉大な先輩、新田次郎氏の著作に「聖職の碑」(せいしょくのいしぶみ)がある。ごぞんじの方も多いだろう。映画化もされ、登山中に遭難したとき教師が教え子を嵐から守るときに「この子たちは…私の命だ!」と叫び、自らの命を賭して生徒たちを守ろうとする、教師とはこういうものなのだ、と諭された映画だった。
教師は生徒のことを慈しみ、生命をかけてまで守る、
ゆえに生徒は無条件に教師を信頼し、教えに従う。
だから、教職というのは「聖職」だった。
だから、教師は「先生」とよばれ、社会から尊敬された。
それが当たり前の時代が、たしかにこの国にはあった。
いつのころからか、教師は尊敬されなくなり、家庭で教えるべきことまでも要求され、余分な事務仕事を押し付けられ、子供と親身にふれあう時間も余裕までも奪われてしまった。
教職はサービス業じゃない!みんな勘違いしてないか?
小学校時代、大好きな先生がいた。半日つぶして感動した映画の話(ベン・ハー)を子供たちに聞かせたり、雪が降ったら校庭に巨大な雪像を作らせたり、破天荒だった。悪さをすると、思いきりビンタをされた。悪いことは悪い、はっきりしていた。子供がその先生にしかられて文句を言うような父兄は一人もいなかった。
家庭訪問でその先生がうちの母に言ったセリフをよく覚えている。「いやぁ、ゆきおはおれがいくら殴っても泣かねえんだよなぁ。」それに応えたうちの母のセリフ、「そうですか、先生。じゃあもっとなぐってやってください。」…… なんちゅう人たちだ!、と子供心に思ったが、殴られた理由もわかっていたし、なによりもその先生のことも母のことも大好きだったから口答えできるはずもなかった。
むしろ、うれしかった。
人前で泣かないはずの僕は、その先生がほかの学校に移られる時、通信簿を渡されるとき、泣いた。もう、ぼろぼろだった。3年の終わりだった。クラス全員と、きっと先生も泣いていた。
教育現場の崩壊が叫ばれて久しい。豊かさを得てそのかわりに失ったものはとてつもなく大きい気がする。教育の崩壊と医療の崩壊はよく似ている。
誤解や批判を恐れずに書かせていただくならば… 前に書いたように、
「教育」と「医療」は『聖域』だとおもう。
学校の先生とお医者さんは『聖職』だと思う。
だから、『先生』と呼ばれ尊敬される。
先生たちの自覚ももちろん大事だが、そうきちんと認識する社会であるべきじゃないだろうか?
学校や教師に因縁を付ける”モンスターペアレント”、
病院や医師・看護師に嫌がらせをする”モンスターペイシェント”ってのがいるらしい。おかしくないか?
このままだとこころ(心、精神)もからだ(体、肉体)もだめな人ばっかりになっちゃうよ。
いいの?
このままだと心ある教師も医師も看護師もいなくなっちゃうよ。
ほんとにいいの?
もう一つの『先生』と呼ばれる人たち:政治家と、
これを読んでくださったみなさんにご一考いただきたい。
この国が本当にダメになっちゃう前に。
2008年2月3日日曜日
聖職の碑